京都「詩仙堂」江戸時代の風流人が建てた山荘はさすがのセンス。
京都は左京区、叡山電鉄「一乗寺駅」下車、徒歩10分ぐらいの「詩仙堂」は石山丈山の山荘。
石山丈山は江戸初期の風流人。元々は徳川家康に仕える武将でしたが、
「大阪の陣」のあと、隠棲することに。
儒学、朱子学者でもあり、師匠は藤原惺窩。林羅山とも親交が深かった。
歌を詠み、書道、作庭が好きで、多岐にわたって才能を発揮した。
いまで言えば、学者であり、小説家であり、空間デザイナーでもあるマルチクリエイターと言えるかも。
さらに、煎茶の祖といわれるように、茶を初めて煎じた人とも言われる。
そんなセンスの塊のような人が作った山荘、当然センスがいい。

一乗寺駅からの道。詩仙堂への道中もなんか雰囲気いいです。

このいい感じの入り口。
石山丈山が生きた安土桃山時代から江戸時代初期は、完全に侘び寂びがブーム真っ只中。
その影響を色濃く反映してます。

竹林の中を抜けるアプローチがまたいい。
篭る感じがいかにも鄙びていい感じ。

詩仙堂は別名「砂の山荘」。って誰も言ってないですけどね笑。
個人的にはそう言ってもいいぐらい砂が印象的。

安土桃山文化の絢爛豪華な世界から、茶の湯的侘び寂びの世界に移行していったんですねー。

障子窓の形がすでにおもしろい。
簡素ながら独自の世界観がぷんぷんです。

すっきりとした砂の庭。空っ風が吹いて来たらどうすんだろう。
あまり風が吹かない京都だから可能にした庭園だなー。

建物の入り口や縁側への入り口の上部がアーチを描いていて、なんだかやさしい印象。
リラックスできる山荘だなー。うらやまし過ぎるぞ、丈山!

石の配置、竹垣、植木のバランスの手が込んでる。

木材、土、石だけで作られた山荘。これは維持だけで大変なんだろうな。

瓦と茅葺き屋根、あちこちいろんな素材を使っていて、見てるだけで飽きない。
屋根の上には物見台? ベランダみたいのもあったりでかなりおもしろい建造物。

茅葺き屋根、機能的にいるかな?笑
もはやデザイン的な欲求でつけたんだろうな。

隠居の家としては最高にいいよな。

庭と建物が一体化したかのような佇まい。超開放感。
逆に夏は蚊がすごそうだけど笑。
まるまるとした植木がまた和む。

庭正面。このまま庭に降りて行きたくなるけど、絶対ダメだ。。

シンと静まり返った砂の庭。心落ち着くー。

縁側からジャンプして、砂の上に着地したい衝動を抑えるのに必死。

なんだかこんもりした草一つ一つが本当は生きていて、じっと静かにしてるように見えてきた笑。

庭がまた、散策するのが楽しい庭。
いろんな種類の植物が植えられて、それぞれいい味出してます。

自然の発色って生きてるだけあって、ビビッドだな。

庭の中を小さな小川が流れていたり、あちこち趣向が張り巡らされております。

池も波紋一つ立てず静寂そのものだったり。

いろいろな草木で作る小道が歩いていて楽しい。

詩仙堂と言えば、看過できないのが「ししおどし」。
日本で初めて発明された場所ですから。
山の傾斜に立つ詩仙堂は、イノシシや鹿がすぐ山から出てきたらしく、
困った石川丈山が発明したそうです。カコーン。

夕暮れ時はこれまたいい雰囲気。和むなー。

苔むした蹲もワビってる、サビってる。

ぽとんと落ちた椿の花がまたかわいらしい。自然が作る美ってすばらしい。
詩仙堂
叡山電鉄「一乗寺」駅下車 徒歩約10分
市バス・京都バス「一乗寺下り松町」下車 徒歩約8分
9時~17時
500円
京都市左京区一乗寺門口町27番地
075-781-2954
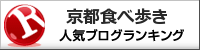
京都食べ歩き ブログランキングへ
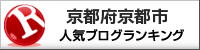
京都府京都市 ブログランキングへ
![]()
にほんブログ村
![]()
にほんブログ村



